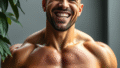1. はじめに ― 「よく眠ること」は、最高の美容と健康法

夜ぐっすり眠れた翌朝は、肌の調子が良かったり、頭がすっきり冴えていたりしませんか?
実は「よく眠ること」は、食事や運動と同じくらい、心と体を整えるために欠かせない習慣です。
質の良い睡眠は、日中のパフォーマンスを高め、代謝を整え、ホルモンバランスを安定させる働きがあります。
反対に、睡眠が乱れると集中力や記憶力が落ち、肌荒れ・体重増加・気分の落ち込みなどのトラブルにつながることも。
たとえば、ある研究では睡眠時間が6時間を下回ると、注意力や反応速度はアルコールを摂取した状態と同程度まで低下するといわれています。
また、睡眠不足が続くことで血糖値のコントロールが乱れ、生活習慣病のリスクも上がることが確認されています。
つまり、睡眠は「休む時間」ではなく、明日をつくるための再生の時間。
夜の過ごし方や朝の起き方を少し変えるだけで、眠りの質は確実に変わっていきます。
この記事では、Glow Styleが提案する「よりよく眠るための生活習慣」について、
夜の準備から朝の目覚めまで、すぐに取り入れられるアイデアを紹介していきます。
2. 寝る前の過ごし方 ― 質のいい眠りの準備を
「寝る時間になってもなかなか眠れない」
「ベッドに入ってからスマホを見てしまう」
そんな悩みを持つ人は多いのではないでしょうか。
実は、眠る“直前の過ごし方”こそが睡眠の質を決めるカギ。
体と心を“眠るモード”にゆるやかに切り替えていく時間が大切です。
● 寝る直前の入浴は避けて、90分前の「温めリセット」を
お風呂は眠る準備に最適なリラックスタイムですが、寝る直前に入ると逆効果になることもあります。
人は体温が下がるときに眠気を感じやすくなるため、入浴で一度温めてから、ゆっくりと体温を下げていく流れが理想です。
おすすめは「就寝の1時間半前」くらいのタイミング。
湯温は38〜40℃のぬるめに設定し、肩まで浸かって10〜15分程度が目安です。
お風呂から上がったあとは、明るい照明を避けて、やさしい光の中で過ごしましょう。
● 寝る前の食事・カフェインは控えめに
食事をとると消化のために内臓が活発に働くため、寝つきが悪くなったり、睡眠が浅くなったりします。
特に、脂っこい料理や糖分の多いスイーツは、血糖値を乱しやすいので要注意。
理想は就寝の2〜3時間前までに夕食を済ませること。
どうしてもお腹が空いてしまうときは、温かいスープやナッツなど、消化に優しいものを選びましょう。
また、コーヒーや紅茶に含まれるカフェインは4〜6時間ほど作用が残るため、夕方以降は控えるのがおすすめです。
● 寝室は「暗く・静かに・心地よく」

睡眠ホルモン・メラトニンは光にとても敏感です。
寝室をできるだけ暗くし、スマホやテレビの明かりをオフにすることで、自然に眠気が訪れます。
もし完全な暗闇が落ち着かない場合は、オレンジ系の間接照明をほんのり灯してもOK。
また、寝具の触感や香りも眠りの質に影響します。
柔らかすぎず、体を支えるマットレスや清潔なシーツを選び、
ラベンダーやベルガモットなどのリラックス系アロマを使うのも効果的です。(Amazonリンク)
● スマホを手放す「デジタルデトックス」
寝る前のスマホ操作は、脳を覚醒させるブルーライトによって眠りを妨げます。
SNSやニュースをチェックすると、気づかないうちに心が緊張モードになってしまうことも。
理想は就寝の30分前にはスマホを置くこと。
その時間を、読書やストレッチ、軽い瞑想に充てると、自然と呼吸も深まり心が落ち着いていきます。
(Amazonリンク ー タイムロッキングコンテナ スマホ )
寝る前の1時間を「明日の自分を整える時間」として過ごすことで、
眠りの深さも、翌朝の目覚めの軽さも、少しずつ変わっていきます。
“いい眠り”は、寝る前から始まっているのです。
3. 寝室の環境づくり ― 光・音・温度のコントロール
快適な眠りを得るためには、寝室の環境を整えることが欠かせません。
どんなに入浴や食事に気をつけても、眠る空間そのものがストレスを生む場所では、体も心も休まりません。
理想の寝室は、体のスイッチが“おやすみモード”に切り替わる静かな場所。
ここでは、眠りを誘う空間づくりのポイントをご紹介します。
● 照明は「オレンジ系のやさしい光」に
寝室の照明は、明るすぎず、暖色系の光を選ぶのがポイントです。
蛍光灯のような白い光は脳を覚醒させてしまうため、
間接照明やスタンドライトを使い、光源を直接見ない工夫を。
夜のリラックスタイムには、色温度2,700K以下の電球色ライトがおすすめ。
視覚的にも心が落ち着き、自然と眠りに導かれます。
● 室温と湿度のバランスを整える
人が快適に眠れる環境は、**室温18〜22℃、湿度50〜60%**が目安。
寒すぎても暑すぎても眠りが浅くなってしまいます。
冬場は加湿器や湯たんぽを活用し、乾燥による喉の痛みを防ぎましょう。
夏はエアコンの冷風が直接体に当たらないよう、タイマー機能やサーキュレーターを上手に使うのがコツです。
● 寝具は「包まれるような安心感」を大切に
寝具選びは、眠りの質を大きく左右します。
マットレスは柔らかすぎると体が沈み、硬すぎると肩や腰に負担がかかります。
体をしっかり支えつつも、自然な寝姿勢を保てるものを選びましょう。
また、枕の高さが合っていないと、首や肩のこりの原因になります。
横向きで寝る人はやや高め、仰向けの人はやや低めを目安に。
季節ごとにカバーを替えて、**肌触りのよい素材(コットン・リネンなど)**を使うとさらに快適です。
● 香りと音で「五感をととのえる」
香りや音は、睡眠の質を高める“隠れた名脇役”です。
ラベンダーやカモミール、ゼラニウムなどのアロマオイルをディフューザーに数滴たらしてみましょう。
自然な香りが脳をリラックスさせ、眠りに入りやすくしてくれます。
また、静寂が苦手な人は自然音(波の音や雨音)やヒーリングミュージックを小さな音量で流すのもおすすめ。
副交感神経が優位になり、心拍数が穏やかに整っていきます。
● 寝室を「眠るためだけの空間」に
ベッドの中でスマホを見たり、仕事のメールを確認したりしていませんか?
脳は「この場所=活動する場所」と覚えてしまうため、寝室でのオン・オフが曖昧になると眠りに入りにくくなります。
できれば寝室では、“眠る・休む”以外の行動をしないことが理想です。
ベッドに入ること=休息、という条件づけを続けることで、
体が自然に“眠る準備”を始めてくれるようになります。
眠りは、体の修復だけでなく、心をリセットする時間でもあります。
自分を整えるための“静かな場所”として寝室を育てていくことで、
次の日のパフォーマンスも、人生の質も、少しずつ変わっていくでしょう。
4. 「寝る姿勢」と「寝返り」のバランスを整える
ぐっすり眠れない原因のひとつに、「寝る姿勢の悪さ」や「寝返りの少なさ」があります。
寝ている間に体が痛くなったり、朝起きたときに肩や腰が重いと感じたことはありませんか?
それは、同じ姿勢のまま長時間寝ていることで、血流が滞っているサインかもしれません。
眠りの質を高めるためには、「どんな姿勢で眠るか」だけでなく、「どのくらい寝返りを打てているか」も大切なんです。
● 理想的な寝姿勢は「まっすぐ自然体」
理想の寝姿勢は、**立っているときの姿勢をそのまま横にしたような“まっすぐ自然体”**です。
背骨が緩やかなS字カーブを描き、首・肩・腰に負担がかからない状態が理想。
- 仰向け寝:体重を均等に分散でき、筋肉がリラックスしやすい。
- 横向き寝:いびきや無呼吸の予防に◎。右を下にすると胃の負担も軽減。
- うつ伏せ寝:呼吸が浅くなりやすく、首や腰に負担がかかるため、できるだけ避けましょう。
自分に合った枕やマットレスを使うことで、この自然な姿勢を保ちやすくなります。(Amazonリンク)
● 寝返りは「眠りの質」を保つスイッチ
寝返りは、ただ体を動かしているだけではなく、血流や体温を調整するための大切な動きです。
寝返りを打つことで圧迫された部分の血行を回復させ、筋肉をほぐし、深い眠りを保ちます。
もし朝起きたときに体の一部がこっていたり、しびれていたりする場合、
マットレスが柔らかすぎて体が沈み込んでいる可能性があります。
体の動きを妨げない、反発力のある寝具を選ぶと、寝返りが自然に打ちやすくなります。
● 良い寝返りをサポートするコツ
寝返りをスムーズにするには、以下のような小さな工夫が効果的です。
- 枕は肩まで支えるように置き、首の角度が無理のない高さにする。
- 寝る前に軽くストレッチをして、肩・背中・腰の筋肉をほぐしておく。
- パジャマはゆったりとしたものを選び、寝返りの妨げにならないようにする。
また、枕の位置を少しずつ調整して、自分にとって一番自然に寝返りを打てるポジションを探してみましょう。
● 「静かな眠り」より「動ける眠り」を意識する
ぐっすり眠る=まったく動かない、というイメージを持つ人も多いですが、
本当に良い眠りとは、体が必要に応じて自然に動ける眠りのことです。
寝返りを打てるということは、体が緊張せず、深いリラックス状態にあるという証拠。
つまり、静止した眠りよりも“動きのある眠り”のほうが質が高いのです。
朝目覚めたときに、体が軽く、頭がスッキリしているなら、それは良い寝返りができていた証。
自分に合った寝姿勢を見つけ、寝返りを妨げない環境を整えることで、
体の疲れがスムーズにリセットされ、翌朝の目覚めも心地よくなります。
眠りは「動」と「静」のバランス。
完璧に動かない眠りよりも、自然な動きを受け入れる眠りを目指しましょう。
5. 朝の起き方 ― 目覚めを“心地よく”する習慣
朝、アラームの音で無理やり目を覚ますのがつらい――。
そんな経験、誰にでもありますよね。
しかし実は「起き方」ひとつで、その日の体調や気分、集中力までもが変わります。
心地よい目覚めの習慣を身につけることで、一日のスタートをぐっと軽やかにできるのです。
● スヌーズより「一発起き」を目指す
アラームを止めてはまた鳴らす“スヌーズ地獄”は、実は睡眠の質をさらに悪くしてしまいます。
短い時間の二度寝は深い眠りに入れず、体と脳が「寝たいのに起こされる」ストレスを感じるからです。
おすすめは、
- アラームを1回だけ鳴るように設定する
- ベッドから少し離れた場所にスマホを置く
- 「起きたらカーテンを開ける」「水を一口飲む」など、最初の行動を決めておく
これだけで、朝の「ダラダラ時間」が自然となくなります。
● 朝日を浴びて体内時計をリセット
朝起きたらまずカーテンを開けて自然光を浴びることを習慣にしましょう。
太陽の光には、体内時計をリセットしてくれる効果があります。
光を浴びてから約14〜16時間後に眠気を誘うホルモン「メラトニン」が分泌されるため、
夜の眠りもスムーズになるんです。
また、光を浴びることでセロトニン(幸福ホルモン)が活性化し、
気持ちが前向きになり、朝のストレスが軽減される効果もあります。
冬や天気の悪い日は、光目覚まし時計を使うのもおすすめです。
Amazonなどでも手軽に購入でき、自然な朝日を再現してくれます。(Amazonリンク)
● 起き抜けの“1杯の水”で内側からスイッチON
睡眠中はコップ1杯分ほどの水分が失われています。
起きてすぐの水分補給は、体をゆっくり目覚めさせ、代謝をスタートさせるスイッチのようなもの。
冷たい水ではなく、常温またはぬるめの水をゆっくり飲むのがポイントです。
内臓が温まり、血流が促進され、頭も体もスッキリと動き出す感覚が得られます。
朝一番の水で体を整える|代謝アップと健康につながるグッドプラクティス – Glow Style
● 朝ストレッチで「動く準備」を整える
眠っている間、体は思っている以上にこわばっています。
起きてすぐに軽く体を伸ばすことで、血流を促進し、
「活動モード」への切り替えをスムーズにできます。
特におすすめのストレッチは、
- 手を頭の上で大きく伸ばす
- 首をゆっくり回して肩をほぐす
- ベッドの上で軽く背伸びをする
この3つだけでもOK。
無理に動かそうとせず、「心地いい」と感じる範囲で行うのがコツです。
● 朝の音と香りで“感覚から目覚める”

五感を刺激することも、心地よい目覚めには効果的です。
静かな音楽や自然音(鳥の声、波の音など)を流すと、副交感神経から交感神経への切り替えがスムーズに。
また、アロマの香りを取り入れるのもおすすめです。
- 柑橘系(レモン、オレンジ):気分を前向きにする
- ペパーミント:頭をスッキリさせる
- ローズマリー:集中力アップ
朝のルーティンに「香り」を加えるだけで、毎日のスタートが少し特別になります。
● “気持ちよく起きる”は“気持ちよく眠る”から始まる
実は、朝の目覚めの質は前日の夜の過ごし方で決まります。
寝る前にスマホを見すぎない、食事を早めに済ませるなど、
「眠りの準備」を整えておくことで、翌朝スッと目が覚めるようになります。
朝のルーティンを変えることは、自分の体と心のリズムを整える第一歩。
一日の始まりを“心地よく”迎える習慣を、今日から少しずつ取り入れてみましょう。
6. 生活リズムを整える ― 良い睡眠のための昼間の過ごし方
「夜よく眠れない」と感じるとき、
つい“寝る前の過ごし方”だけに目が行きがちですが、
実は昼間の過ごし方こそが、夜の眠りを左右する最大のポイントです。
日中に体をどれだけ動かしたか、光を浴びたか、どんなリズムで過ごしたか――。
その積み重ねが「眠る力」を育てていきます。
● 朝・昼の“光”を味方にする
朝日を浴びることの大切さは先ほども触れましたが、
実は昼間にもしっかりと明るい光を浴びることが、
夜の眠気を自然に導く鍵になります。
特にオフィスや室内にいる時間が長い人は、
ランチタイムに5〜10分でも外に出て、自然光を浴びるのがおすすめ。
曇りの日でも屋外の光量は室内照明の10倍以上あり、
体内時計を安定させる効果があります。
● 昼寝のタイミングは“15分以内・午後3時前”が理想
午後の眠気をリセットしたいとき、短い昼寝はとても有効です。
ただし、長く寝すぎると夜の睡眠リズムを崩してしまうことも。
おすすめは、
- 15〜20分以内の短い昼寝
- 午後3時までに済ませること
コーヒーを飲んでから昼寝すると、
ちょうどカフェインが効き始める頃にスッキリ目覚める“コーヒーナップ”も人気です。

コーヒーナップの意味とは?生産性向上につながる睡眠の質を上げる方法をご紹介 | 栄養・健康・ウェルネス | ネスレ日本 企業サイト | Nestlé
コーヒーの健康効果とは?|カフェインとポリフェノールで未来を整える習慣 – Glow Style
● 適度な運動で「夜の眠りやすさ」をつくる
日中に体を動かすと、体温リズムとホルモン分泌が整い、夜の眠りが深くなります。
とはいえ激しい運動でなくてもOK。
たとえば、
- 駅までひと駅分歩く
- 階段を使う
- 軽いストレッチを習慣化する
これだけでも、夜の「寝つき」が変わってきます。
特に夕方の軽い運動(ウォーキングなど)は、体温が下がるタイミングと眠気が重なり、
自然な入眠をサポートしてくれます。
● カフェインとの上手な付き合い方
コーヒーや紅茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインは、
眠気を抑える効果がありますが、摂取のタイミングを誤ると夜の睡眠に影響します。
一般的にカフェインの効果は4〜6時間ほど持続するため、
夜10時に眠りたい人は午後4時以降の摂取を控えるのが理想です。
どうしても飲みたいときは、
- カフェインレスコーヒー
- ハーブティー(カモミール、ルイボスなど)
を選ぶとよいでしょう。
● 日中の「ストレスリセット」が夜の安眠をつくる
強いストレスや緊張を抱えたままでは、夜に体が“警戒モード”のままになり、眠りが浅くなります。
昼間のうちに、意識的に心をリセットする時間を取りましょう。
たとえば、
- 5分だけ目を閉じて深呼吸をする
- お気に入りの音楽を聴く
- 緑の多い場所で空を見上げる
ほんの短い時間でも、脳がリラックス状態に切り替わります。
Glow Styleとしておすすめなのは、観葉植物をデスクに置くこと。
視覚的な癒しと同時に、空気もやわらかく感じられます。
植物のある生活で、心と空間に潤いを|冬でも楽しめる“おうち温室”のすすめ – Glow Style
● 「昼を整える人ほど、夜がやさしい」
夜ぐっすり眠るための準備は、実は朝から始まっています。
朝の光、昼の動き、夕方の休息――そのリズムを整えるだけで、
体も心も自然に「休む準備」ができるのです。
眠れない夜を嘆くより、まずは**“昼間を整える”意識**を。
それが、Glow Styleが提案する「心地よい暮らし」の第一歩です。
7. おわりに ― “眠りを整えること”は“自分を整えること”
睡眠は、ただ体を休めるだけの時間ではありません。
それは、心と体を「リセットし、再び前へ進むための準備の時間」。
忙しい毎日の中で、私たちはつい“効率”や“生産性”を優先してしまいがちです。
けれど、本当に力を発揮できるのは、しっかりと休息をとれたとき。
睡眠は、人生をより良くするための**“静かな投資”**なのです。
● 完璧を目指さず、“整える”ことを意識して

理想の睡眠習慣を一度に手に入れるのは難しいもの。
それでも、
- 寝る前のスマホ時間を5分減らす
- 朝に少しだけ光を浴びる
- 寝室を少し暗くしてみる
――そんな小さな変化を積み重ねるだけで、確実に眠りは変わります。
睡眠を整えるということは、つまり自分のリズムを取り戻すこと。
その積み重ねが、日々の活力や前向きな気持ちへとつながっていきます。
● 眠りが変われば、世界が少しやさしくなる
よく眠れた朝は、不思議と景色まで違って見えるもの。
昨日までの悩みが少し軽く感じられたり、人にやさしくなれたり。
それは、心が穏やかに整った証拠です。
Glow Styleでは、「心と体の調和」を大切にしています。
睡眠を整えることは、その第一歩。
“よく眠れる自分”をつくることで、“よりよく生きる自分”に近づいていく――
そんな未来を、私たちはあなたと一緒に目指しています。
✨ Glow Styleとともに、理想の眠りと、理想の自分へ。
今日からできる小さな習慣で、あなたの毎日をもっとやさしく整えていきましょう。